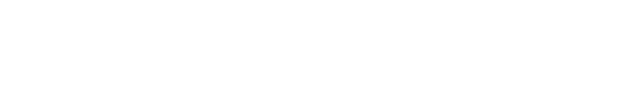犬は臭いでパーキンソン病かどうかを検知できるかもしれない、という研究
イギリスから、犬を訓練してパーキンソン病の有無が検知できるかどうかを調べたユニークな研究が発表されました(PMID: 40659046)。
研究内容は以下の通りです。
パーキンソン病(PD)の確定診断には未だ決定的なバイオマーカー(病気の有無や程度を客観的に判断するための生体内にある物質、例えば血液検査で分かるような物)が存在せず、早期診断が困難です。過去の研究では、パーキンソン病患者の皮脂には特有のにおいがあると報告されており、これを訓練された犬が検出できる可能性が示唆されています。
目的
本研究では、訓練された犬が、薬物治療前のパーキンソン病患者の皮膚から採取した乾燥皮脂サンプルを用いて、健常者や他の神経疾患患者との区別ができるかを二重盲検法で検証しました。
方法
2匹の犬(ゴールデンレトリバー系)を約10ヶ月訓練。
訓練には計205件のサンプル(パーキンソン病患者130、対照群175)を使用。
最終試験は、40名の患者(すべて薬物未使用)と60名の対照群からのサンプル100件を用い、完全にブラインドで実施。
結果
Dog 1:感度70%、特異度90%
Dog 2:感度80%、特異度98.3%
感度とはパーキンソン病かどうかを検知する精度、特異度は犬の判断の正確さです。
このように2匹の犬は、統計的に有意に正確にPD患者のにおいを区別できました。
ちょっと突飛な研究のように見えますが、それなりに根拠はあります。
パーキンソン病患者さんでは皮脂の分泌が亢進し、脂漏性皮膚炎のような病状を呈することがあります。またパーキンソン病ではα-シヌクレインという蛋白質の蓄積が病気の原因と考えられていますが、このα-シヌクレインは皮膚にも蓄積することが分かっているので、それが皮脂分泌に影響している可能性があります。他にも、パーキンソン病では脳より先に腸管から病気が始まることが多く、腸内細菌叢に変化があるという報告もあります。腸内細菌は皮脂分泌に影響を与えますので、こうした機序により病気に特有な皮脂の変化が出るのかもしれません。
訓練の手間を考えると、この方法が一般に普及するのは難しいと思いますが、皮脂の中に診断の手がかりとなる成分がある可能性があり、将来はそれを分析器で分析できるようになるかもしれません。