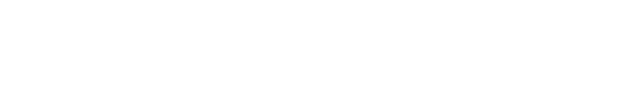運動によりパーキンソン病の進行を遅らせることができる
患者さんから「運動した方が良いですか?」とよく聞かれます。ほとんどの病気で運動はしないよりした方が良いとは思いますが、実際にパーキンソン病患者さんが運動することにより、進行を遅らせることが出来るのでしょうか?
京都大学から2022年に「初期パーキンソン病患者における定期的な身体活動と運動習慣の長期的効果(和訳)」という報告が出ています(PMID: 35022304)。
この論文は要約すると以下の通りです。
【研究の背景と目的】
パーキンソン病は、手足のふるえや歩行の不安定さなどの運動症状を特徴とし、進行すると薬では治しきれない症状(姿勢の崩れや認知機能の低下)が出てきます。これまで運動が症状の改善に良いとされてきましたが、「本当に長い目で見て効果があるのか」「どんな運動がどの症状に良いのか」については、はっきりわかっていませんでした。そこでこの研究では、長期間(最大6年間)にわたり、初期のパーキンソン病患者が日々どれくらい身体を動かしていたかと、その後の病気の進み具合との関係を調べました。
【研究の方法】
アメリカを中心に行われている「PPMI」という大規模な国際研究データを用い、237人の初期パーキンソン病患者を対象にしました。参加者は、毎年「PASE(高齢者用身体活動質問票)」というアンケートで、どのくらい身体を動かしていたか(家事、趣味、運動、仕事など)を自己申告しています。その運動量の平均値と、病気の進行(歩き方や姿勢の安定性、日常生活動作、認知スピードなど)との関係を、専門的な統計手法で分析しました。
【主な結果と発見】
運動を始めた時点(ベースライン)の運動量は、将来の病気の進行とはあまり関係がありませんでした。しかし、「定期的に運動や身体活動を続けていた人」は、以下の点で病気の進行がゆるやかでした:
歩行や姿勢の安定性
日常生活動作(例:食事や着替え)
認知機能(特に処理スピード)
さらに、どのような活動がどの機能に効くかもわかりました:
運動(ジョギングやスポーツなどの中~強度の活動):歩行やバランスの維持に効果的
家事(掃除や洗濯など):日常生活能力の低下を防ぐ
仕事関連の活動(有償・無償の活動):認知処理スピードの低下を抑える可能性
【研究の意義】
一度運動を始めるだけではなく、継続的に身体を動かすことが、パーキンソン病の進行を遅らせるカギになることが明らかになりました。また負荷の高い運動でなくても、家事や仕事に関連したことでも一定の効果があることや、薬では治しにくい姿勢・歩行障害や認知機能の低下といった症状に、運動の効果が期待できる点は注目すべきです。
【実生活へのメッセージ】
パーキンソン病の方は、無理のない範囲で毎日体を動かすことが大切です。散歩、家事、ガーデニングなども立派な運動です。続けることが大切なので、自分に合った方法を見つけて習慣化することが成功のカギです。特に歩く力や認知力が気になる方は、軽いスポーツや趣味的な活動(例えばダンス、太極拳など)も検討するとよいでしょう。
パーキンソン病に効果がある運動は、全身を使うもの、リズムがあるもの、機械的な一定の反復運動ではなく自分で考えておこなう運動が良いとされています。私の患者さんで、和太鼓をされている方がいますが、和太鼓は運動ではないですがこうした条件を満たしていますね。無理のない範囲で自分が楽しめることを続けることが重要です。