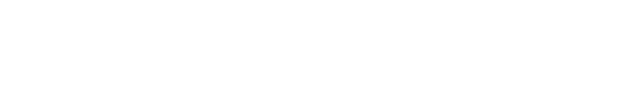パーキンソン病の原因が“腎臓”にあるかもしれないという研究
腎臓の働きの低下がパーキンソン病の発症の要因になるかもしれないという研究が中国から発表されました。
パーキンソン病の原因の一つとして「αシヌクレイン」というたんぱく質が脳内に蓄積するためだと考えられています。
これまでは、αシヌクレインは腸などの消化管や鼻の神経から脳へ広がると考えられてきました。しかしこの研究では、「腎臓も出発点の一つになりうる」という新しい証拠が発見されました。
この研究では以下のことが示されています。
- パーキンソン病や腎不全の患者の腎臓にαシヌクレインの異常なたまりを確認した。
- 腎臓に異常があるマウスにαシヌクレインを注射すると、腎臓だけでなく脳にも広がり、パーキンソン病のような運動障害が現れた。
- 腎臓と脳は神経でつながっており、腎臓から脳へと異常たんぱく質が「神経を通じて移動する」ことが示唆された。
- 赤血球に多く含まれるαシヌクレインが血中に漏れ出て腎臓にたまり、そこから脳へ悪影響を与えている可能性がある。
- 腎臓の神経を切る(腎交感神経切断)と、αシヌクレインは脳まで届かなくなる。
慢性腎臓病の患者さんはパーキンソン病のリスクが高いと以前から言われていましたが、「なぜか」は分かっていませんでした。今回、そのメカニズムが明らかになった可能性があります。腎臓がうまく働かなくなると、体にたまったαシヌクレインを分解できず、結果として脳まで影響が及ぶという仕組みが想定されます。将来的に、血液中のαシヌクレインを除去する治療法や、腎機能を保つことがパーキンソン病予防につながる可能性があります。
パーキンソン病は個人差の大きい病気です。症状や進行速度などの個人差は大きく、また発症年齢によっても進行は異なります。早い人では50歳頃に発症しますが、この時点で腎臓の働きが低下している人はあまりいません。むしろ高齢(75歳以上)発症の患者さんでは、腎機能低下が発症に寄与している可能性があります。 発症の経路が多様であることが症状やその後の進行に個人差が大きいことの理由かもしれません。