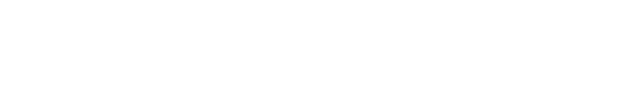パーキンソン病とムクナ豆
パーキンソン病の患者さんから時々、「知人からムクナ豆を勧められたのですが、どうなんでしょうか?」と聞かれることがあります。
ムクナ豆はインド原産のマメ科の植物で、パーキンソン病に効果があることが知られています。最近も和歌山県立医大から、ムクナ豆のパーキンソン病に対する効果を調べた論文が発表されました。
「パーキンソン病に食用の豆が有効 日本のクロスオーバー試験でLD/CD配合錠を上回る有効性」
この論文によれば2008年に和歌山県農業試験場でムクナ豆の栽培に成功したそうなので、和歌山県立医大が研究をしたのは、そうした理由があったのかもしれません。
ムクナ豆のパーキンソン病に対する効果を報告した研究はこれが初めてではなく、2017年にもNeurologyという脳神経内科では権威のある国際誌に、イタリアからの研究が報告されています(PMCID: PMC5539737)。
ムクナ豆がパーキンソン病に効果があるのは、レボドパという物質が含まれているためです。このレボドパは患者さんが服用しているメネシットやイーシー・ドパールという薬と同じ成分なので、ムクナ豆がパーキンソン病に効果があるのは当たり前といえば当たり前で特に魔法の食品ではないのです。
和歌山県立医大の報告では、7名のパーキンソン病患者さんにレボドパと同じ量のレボドパを含有しているムクナ豆を交互に1回ずつ、1週間空けて投与しています。
結果としては、同じ量のレボドパを含むムクナ豆を投与したにもかかわらず、ムクナ豆を服用したときの方が効果が長く続いています。また、この研究ではムクナ豆にレボドパの分解を促すCOMTという酵素の働きを抑える成分があり、そのために同じ量のレボドパよりも、より血中濃度が上がり効果が長く続くのではないかと推察しています。実際、COMTという酵素の働きを抑えることによりレボドパの効果を延長させる薬も存在します(今回の報告では使用されていません)。
またレボドパの血中濃度が上がるとジスキネジアという不随意運動が起こりやすくなりますが、ムクナ豆を服用すると血中濃度はレボドパを服用した時より上がりますが、ジスキネジアは同等でした。過去のイタリアからの論文でも、この逆説的な現象が報告されており、ムクナ豆にはジスキネジアを抑える作用があるのかもしれません。
では、パーキンソン病患者さんはムクナ豆を服用した方が良いのでしょうか?
まず、今回の研究では参加した患者さんは7名と少数でこれだけの数でははっきりしたことは言えません(薬の治験では通常何百から何千人の方が参加します)。またムクナ豆は健康食品であり医薬品ではないので、医薬品ほど厳密な品質管理は要求されていません。つい最近、小林製薬が販売した紅麹サプリで大規模な健康被害が出たことを覚えている方も多いと思います。これまでムクナ豆の効果を調べた研究・報告はいくつかありますが、いずれも今回の報告と同様に短期的なものです。実際にパーキンソン病の治療に使うとなると、年単位になります。そのような長期で、現在使われているレボドパ製剤を上回るメリットがあるかどうかは分かりません。また、他のパーキンソン病治療薬との併用についても安全性はまだ分かっていません。さらに言えば、健康食品なので保険が効かないため、毎日それなりの量を服用するとなると結構お金がかかります。
患者さんから聞かれたときは「積極的には勧めませんが、どうしても試してみたいのであればご自身の判断でどうぞ」とお話ししていますが、実際に長期で服用した方はほとんどいませんでした。理由としては、あまり効果が感じられない、あるいはコストが理由です(1名だけ長期にわたり服用している方がいました)。
これを読まれた方で服用してみたいと思っても、必ず主治医と相談して自身の判断で勝手に服用はしないでください。前述したように、決して魔法の食品ではありません。