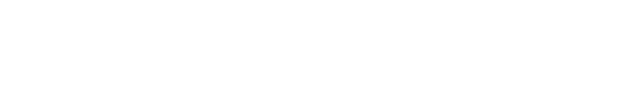パーキンソン病の幹細胞治療
2018年に京都大学がパーキンソン病に対するiPS細胞による治療を発表し、私が診ている患者さんからも「私は治験に参加できますか?」「これでパーキンソン病は治る時代になったんですね?」といった質問を受けましたので、パーキンソン病の幹細胞治療について説明したいと思います。
パーキンソン病は脳の黒質という部位の神経細胞が減る病気です。この神経細胞はドーパミンという物質を作っており、ドーパミンが減ることにより様々な症状がおこります。現在、レボドパ配合錠という薬を服用することにより、不足したドーパミンを補充することが治療の主体になっています。
「パーキンソン病の原因は? 大塚製薬」
では、ドーパミンを産生する細胞が減っているのなら、その細胞を補充すれば病気は良くなるのではないでしょうか?1980年代には、すでにこのように考えた人達がいて、細胞移植の治療がおこなわれてきました。当時の細胞移植は、流産した胎児の脳にある黒質の神経細胞を移植するというものでした。この治療にはいくつかの問題点がありましたが、最大の問題点は胎児の脳を使用するという倫理的な問題です。このため、この治療は北欧、南米の一部の国でしか行われませんでした。また一人の胎児から得られる細胞の数は僅かなため、1人のパーキンソン病患者さんへの移植のために3人の胎児の脳が必要でした。このような理由で、細胞移植が行われた患者数は少なかったのですが、それでも徐々にデータが集まり効果や限界などが明らかになりました。
まず、効果はある程度あることが分かりました。
移植した細胞の大部分は移植後に死んでしまいますが、それでも移植された患者さんの脳に定着し、他の神経細胞とネットワークを作る細胞があることも分かりました。
であれば、倫理的な問題がなく、大量に細胞を用意できればさらに細胞移植による効果が期待できることになります。
では幹細胞とは何なのでしょうか?
cell is holding by a pipet and a neeldle. with clipping path, 3d illustration
ここからは、幹細胞の説明になります。関心がない方は読み飛ばしでください。
生物学には「発生」という概念があります。例えば人間で言えば、まず精子と卵子が結合し胚というものができて、これが分裂を繰り返し徐々に体の形、臓器ができあがっていきます。最初は1個の細胞から始まったものが、プログラムされた遺伝子のオン・オフを繰り返すことにより、脳の神経細胞や、心臓の細胞、肝臓の細胞へと形を変えていきます。また、肝臓の細胞は大人になった後でも分裂しますが、いったん肝臓の細胞になってしまうと、分裂しても間違って神経細胞や心臓の細胞になることはありません。この一連の流れを見ると、ごく最初の段階の胚は、様々な細胞に変化していく力(これを分化と言います)があります。であれば、この胚を使えば、そこから治療に必要な細胞を人工的に分化させて手に入れることができるのではないかという考えが出てきました。この胚を利用した幹細胞が胚性幹細胞(ES細胞)と呼ばれるものです。そして、実際に猿の実験でこのES細胞からドーパミンを作る神経細胞を作り、それをパーキンソン病の猿に移植することにより、症状を改善させることにも成功しました。しかし、ES細胞を利用するためには受精卵が必要であり、人間でES細胞を用いるためには倫理的な問題があるため法制化などが必要で、いったん研究は足踏みします。一方、胚から最終的に分化した細胞への流れは一方向であり、分化のゴールである細胞から流れを逆にすることは不可能と考えられていました。しかし2006年に京都大学の山中教授が線維芽細胞という細胞に複数の遺伝子を組み込むと、幹細胞に変化することをつきとめました。これがiPS細胞です。細胞の分化の流れが、水が高いところから低いところへ流れるように不可逆的と考えられており、人為的にこの流れを逆にできたことは画期的な発見でした。またiPS細胞は倫理的な問題が発生しないこと、日本初の発見であったことから京都大学はiPS研究の拠点となり多額の予算も集まるようになりました。
しかし、iPS細胞による治療にも問題点があります。iPS細胞を作るためには遺伝子操作が必要ですが、これにより細胞が後になって癌細胞に変化してしまう危険性があります。その後、改良が重ねられ現在は癌化する可能性はかなり減っていますが、それでもゼロではないようです。
「iPS細胞とは? 中外製薬」
iPS細胞が適応となる人
ここまでの説明でお分かりかと思いますが、iPS細胞を移植するということは、脳の中にドーパミンを作る細胞を移植しドーパミンを補充するということです。つまり、幹細胞治療というのも、基本的にはこれまで薬物でおこなってきたドーパミン補充療法の延長線上にあるということです。
パーキンソン病の罹病期間が長いと、徐々にドーパミンを補充しても症状が改善しなくなることがあります。幹細胞治療により効果が期待できる人というのは、薬物でドーパミンを補充した場合に反応(改善)がある人ということになります。薬でいくらドーパミンを補充しても反応がない方は、iPS細胞を移植しても改善は期待できません。また、パーキンソン病の症状の中にはドーパミンの不足が関係していない症状があります。例えば、便秘、排尿障害、起立性低血圧などの自律神経障害、嗅覚障害、幻視や認知機能低下などの精神症状などがあります。こうした症状はiPS細胞の移植による改善はあまり期待できませんが、しかし何らかのメカニズムで間接的には多少改善が得られる可能性はあります。
また、高齢者では細胞を移植しても定着率が悪いため、今回の治験では除外されています。
基本的に、今回のiPS細胞移植の治験で適応となる方は、これまで行われてきた脳深部刺激療法の適応がある方と概ね同じです。
1. レボドパの内服(ドーパミン補充療法)に反応がある人
2. 不随意運動(ジスキネジア)が原因で、レボドパをこれ以上増量できない人(薬物療法が限界である人)
3. ウェアリング・オフがあり、日常生活に支障が出ている人
iPS細胞が従来のドーパミン補充療法の延長線上にある治療であれば、薬物療法と比べて何が優れているのでしょうか?なぜ多額の研究費を投じて治験をおこなうのでしょうか?
パーキンソン病の患者さんは、レボドパ配合錠を1日2-6回、人によっては7回以上服用している人もいます。服用回数が多くなるのは、長年レボドパを服用していると、徐々に効果時間が短くなっていくためです。では、1日6回服用している人を考えてみましょう。こうした方は、レボドパを服用すると、すぐに脳内のドーパミン濃度が上昇し、しばらくするとまた下降していきます。次の薬をのむと、またこれの繰り返しになります。つまり以下の図1のように脳内のドーパミン濃度に山谷ができてしまいます。
この山谷が病気をより悪化させるのではないかと考えられており、不随意運動(ジスキネジア)もこの山谷が原因です。脳内のドーパミン濃度はできるだけ、図2のように一定(水平)になることが望ましいのです。iPS細胞から作ったドーパミン産生細胞を脳内に移植すると常に脳内に適切なドーパミンが補充され、この山谷がなくなり一定になるのではないかと考えられています。
これまでに行われた胎児の細胞を用いた移植療法から、ある程度効果はあると予想されます。ただiPS細胞特有の問題もあり、安全性の検証はこれからになります。まずは今回の治験の結果を待つ必要があると思います。
幹細胞移植は決してパーキンソン病を根治させる治療ではないと書きました。しかし、将来にもし幹細胞移植が容易、安全かつ安価になり普及すれば、もっと病気の初期の段階で移植することも考えられます。そうすれば、これまでの内服治療より病気の進行を抑えられる可能性があると思います。
参考文献
森実 飛鳥. パーキンソン病に対する多能性幹細胞を用いた細胞移植治療の現状, 臨床神経, 2019
Parmar M. et al. The future of stem cell therapies for Parkinson disease , Nature reviews neuroscience, 2020